|
北海道病害虫防除所 |
|
平成27年度に特に注意を要する病害虫 |
秋まき小麦のなまぐさ黒穂病
たまねぎおよびねぎのネギハモグリバエ
(1)水稲の紋枯病および疑似紋枯病
水稲の紋枯病は、これまで道内での発生面積率は毎年数パーセントにとどまっていたが、現況調査における発生面積率は平成22年、25年および26年には10%を超え、発生量が増加傾向にある。また、これに加えて疑似紋枯病(6病害の総称)の発生も確認されている。いずれも高温性の病害であり、夏季の高温傾向が発生量の増加に影響していると考えられる。
紋枯病は主として葉鞘に病斑が形成され、病勢が進展するに伴い上位の葉鞘にも病斑が形成されるようになる。止葉の葉鞘や葉身に病斑が及ぶと枯れ上がることもある。病斑が古くなると菌核が形成される。り病残渣および菌核が次年度の伝染源となる。葉鞘から落下した菌核は土壌中で越冬するが、翌年の代かき作業で水面に浮上し、株元に付着して感染する。このため、浮遊した菌核が集まりやすい風下の畦畔沿いなどで発生しやすい。疑似紋枯病は、菌種により病原力に差はあるものの、病徴や伝染源は紋枯病と類似している。
紋枯病の発生が見られた水田では感染源も多くなっていると予想されることから、平成27年の発生にも注意する必要がある。夏季の高温や高湿度により発生が助長されるため、密植を避け過剰な分げつとならないよう栽培法にも注意する。窒素多肥はイネの抵抗力を弱め、茎葉を繁茂させることによって株内湿度を高めることになるため避ける。毎年本病の発生が見られるような水田では、薬剤による防除を行う。疑似紋枯病は、いずれの菌種も発生生態は比較的類似しており、疑似紋枯症に登録のある薬剤を使用し、使用時期などは紋枯病に準じる。

写真 水稲に発生した紋枯病(中央農試 東岱 原図)

写真 水稲に発生した疑似紋枯病(赤色菌核病) (中央農試 東岱 原図)

写真 水稲に発生した疑似紋枯病(赤色菌核病)(道南農試 三澤 原図)
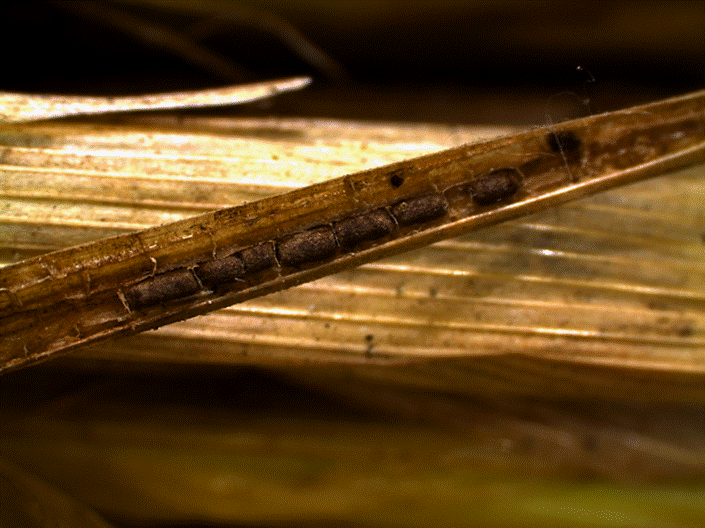
写真 疑似紋枯病(褐色菌核病)の菌核(中央農試 東岱 原図)

写真 疑似紋枯病の初期病徴(道南農試 三澤 原図)

写真 疑似紋枯病による被害(道南農試 三澤 原図)
秋まき小麦のなまぐさ黒穂病は、常発する一部地域を除いて、道内での発生がほとんど確認されていなかったが、平成25年には3振興局内の複数地点で発生が認められ、発生について注意喚起を行ったところである。しかし、平成26年も4振興局管内で発生が認められただけではなく、多発生となった地域もあり、再び問題となった。
平成27年産秋まき小麦では、すでには種作業が終了しており、健全種子の使用、種子消毒の徹底、適期は種など本病に対する基本的技術は励行されたと考えられるが、越冬後については、本病の発生を見逃さないようにすることが重要である。なお、春まき小麦は、道内での発生は未確認であるものの、海外では発生事例が報告されていることから、秋まき小麦同様に注意が必要である。
本病のり病株は健全株に比較し稈長がやや短くなる傾向にあるが、発生が軽微な場合は外観上の識別が難しい。病穂はやや暗緑色を帯び、内部には茶褐色の粉状物(厚膜胞子)が満たされるが、外皮は破れにくいので裸黒穂病のような胞子の露出と飛散はない。病穂は生臭い悪臭を放つので、本病が発生すると減収のみならず、異臭による品質低下を招く。汚染された生産物が乾燥・調製施設に混入した場合、施設全体が汚染されることとなり被害は大きくなるので、本病の発生が認められたほ場産麦は収集施設に搬入しないようにする。また、汚染の拡大を防止するため、発生ほ場の収穫作業はできるだけ最後に行い、麦稈はほ場外にもちださないようにする、機械類などは、作業後洗浄を行い、機械に付着した厚膜胞子や厚膜胞子を含む土壌を除去する。
過去に本病の発生があったほ場、近隣に発生ほ場がある場合などは、出穂後にほ場をよく観察し、本病発生の有無を確認してから収穫作業を実施する。

写真 なまぐさ黒穂病が多発したほ場(円内は発病により丈が短くなった穂(道南農試 田中 原図)

写真 なまぐさ黒穂病に罹病した穂(道南農試 田中 原図)

写真 なまぐさ黒穂病に罹病した穂(中央農試 小松 原図)
ネギハモグリバエは、たまねぎ、ねぎ、にらなどネギ属のみを加害する狭食性の害虫で、北海道を含む全国に分布する。これまで道内での発生量は少なく、大きな被害をもたらすことはなかったが、平成25年に空知、石狩、上川地方のたまねぎで本種による葉の食害が多発し、一部のほ場では幼虫がりん茎に侵入する新症状が発生し、収穫物の品質低下を招いた。
平成26年には、本種による葉の被害が確認された地域は拡大するとともに、地域内における発生ほ場数およびりん茎への幼虫侵入による被害も増加し、本種によるたまねぎの被害が各地で顕在化した。
本種のたまねぎほ場での発生消長は未解明であったことから、空知地方のたまねぎほ場に粘着トラップを設置して調査したところ、5月下旬には成虫の誘殺が認められた。成虫の密度は6月中旬に一旦低下したが、7月上旬から再び上昇し、枯葉期まで高密度で推移した。幼虫の食痕は5月下旬から確認され、加害は8月中旬の枯葉期まで長期間に及んでいた。
平成26年の多発生から本種の越冬密度は高いと推察される。また、平成25〜26年にかけての発生状況をかんがみると、平成27年は発生地域がさらに拡大する恐れがある。
本種に対する防除技術については、平成27年度より具体的に検討することとなっている。現時点では、発生初期の密度を低下させるための5月中旬から6月上旬頃の薬剤防除、りん茎被害を防止するための7月上旬頃から枯葉期までの薬剤防除が重要と推定している。幼虫は葉に潜っていることから薬剤散布による防除効果は得られにくいので、成虫発生時期からの防除を心がける。そのため成虫の初発を見逃さぬよう、5月中旬頃からほ場を観察し、数個から十数個の縦に並んだ白い点状の成虫食痕に注意する必要がある。本種による被害が未発生の地域においても、成虫食痕を目印に本種発生の有無を確認し適切な管理を行う。

写真 ネギハモグリバエの幼虫によるたまねぎの食害(中央農試 武澤 原図)

写真 ネギハモグリバエの成虫とたまねぎの葉に発生した成虫の食痕(中央農試 武澤 原図)

写真 ネギハモグリバエの幼虫によるたまねぎの鱗片の食害(中央農試 武澤 原図)

写真 ネギハモグリバエの幼虫によるたまねぎの鱗片の肩落ち症状(中央農試 荻野 原図)
ホームページへ戻る